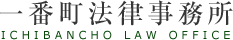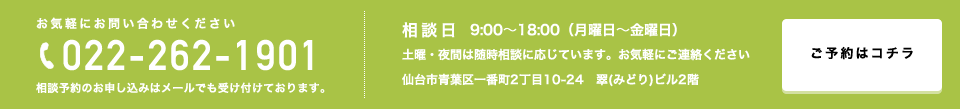1 当事務所の私菊地弁護士と鈴木弁護士で担当していた医療過誤事件で先日、仙台高等裁判所で逆転勝利和解が成立しました。最初の相談 から実に足かけ5年の勝利解決です。
2 事案は以下のとおりです。
東北の○○県のAさん(当時76歳、女性)が平成24年2月○日、誤嚥性肺炎で相手方クリニックに入院しました。その際担当医師は、家族に 対し「一応危篤だけどやれることはやります」と言い、カルテにも「全身状態不良。今後回復については困難」との記載があり、一方的にAさんの救命可能性は低いとの判断のもとに早々に「看取り治療」を決め込みました。しかし、肺炎のガイドラインによれば、Aさんの症状では死亡率は8.2%、悪く見ても29.2%にとどまるものであり、担当医師の上記判断は完全に誤りでした。
担当医師は、肺炎に対する抗菌薬としてピペユンシン(ペニシリン)単剤のみを投与しましたが、ペニシリンだけではペニシリン耐性菌 には有効ではなく(肺炎球菌や黄色ブドウ球菌等の誤嚥性肺炎の原因菌はペニシリン耐性がかなり進んでいる)、ガイドラインではペニシリナーゼ阻害薬やβラクタマーゼ阻害薬を混合配合した薬剤の投与が推奨されています。ピペユンシン単剤を投与することは現在の医療では考えられないことでした。また、相手方クリニックでは入院したAさんに対する適切な酸素療法、適切な水分・電解質管理、栄養管理がなされていない、投薬すべきでない副腎皮質ステロイド薬が投薬されている等、杜撰極まりない治療が行われていました。そして、入院後わずか4日目にAさんの容態は急変し、Aさんの家族(夫のBさん、長男のCさん)は病院からの連絡にすぐに相手方クリニックに駆け付け、駆け付けた時はAさんはすでに心停止状態で看護師が心臓マッサージをしていました。ところが、担当医師はBさん、Cさんよりも15分も遅れてクリニックに悠然と現れ、BさんとCさんに開口一番「私は最初に危篤だと言いましたよね!」と言い放ちました。さらに驚いたことに、同医師は続けて「死体を処理していいですか」と聞いてきました。
こうしてAさんは亡くなってしまいました。死亡診断書の死因は「急性心不全」ですが、3で述べる協力医師によれば死因は「敗血症による心停止」です。
3 相手方クリニック側の対応に不審を抱いた遺族のBさん、Cさんは○○県から当事務所に来られて私に相談をし、とりあえずカルテ等の証拠を確保する必要があるので、○○地方裁判所に証拠保全の申立を行い、同年7月相手方クリニックに赴き証拠保全を実施しました。
そして、私は名古屋の医療事故情報センターに協力医師(内科)を紹介してもらい、保全したカルテ等をその医師に送り、過誤の有無を検討してもらいました。そうしたところ、上記2で指摘したような様々な問題点が指摘され、この医師に署名入りの意見書を作成してもらうことになりました。こうして出来た協力医師の意見書をもとに、Bさん、Cさんは平成25年1月相手方クリニックを被告に○○地方裁判所に約金3000万円の損害賠償請求訴訟を提起しました。この訴訟の途中でAさんの夫であるBさんが亡くなり、長男のCさんが裁判をすべて引き継ぐことになりました。
4 協力医師の説得力ある意見書及び裁判所の審理の経過からして、私は勝訴を確信していましたが、約2年半の審理の後平成27年7月に出された○○地方裁判所の判決は、意外にも請求棄却のCさん敗訴判決でした。
この判決は、確かに、相手方クリニックに抗菌薬投与義務違反、ステロイド薬の投与に関する注意義務違反、水分・電解質管理に関する注意義務違反は認めました。しかし、判決は「敗血症による心停止の前には血圧の高度低下と心筋虚血や不整脈といった前駆症状が先行するところ、本件では患者の心停止の前にこのよう症状は現れていない」として、敗血症による心停止を認めず、上記各種注意義務違反と死亡との因果関係を否定しました。
判決が言う「敗血症による心停止の前に前駆症状が先行する」ことは当方も認めるところで、当方の主張は「心停止前に心電図を記録していなかっただけで前駆症状は先行していた」というものでしたが、判決は「それを認めるに足りる証拠はない」として当方の主張を排斥しました。
Cさんは、この判決を不服として即刻控訴し、舞台は仙台高等裁判所に移りました。
5 控訴審から、当事務所の鈴木弁護士も代理人に加わりました。
控訴審での重要な争点は因果関係の有無です。一審判決が因果関係を否定した根拠がカルテにある心電図波形でした。その心電図波形はフラット(つまり心静止)になっており、心筋虚血や不整脈といった前駆症状を示す波形はカルテには存在しなかったからです。相手方クリニック側は、一審から、「心電図は異常が発生した時に自動記録される。だから、他に心電図が存在しない以上前駆症状は発生しなかった」と主張していました。
しかし、上記心電図をよく見ると、心電図記録時刻は患者のカルテに記載がある死亡時刻の7分後になっていました。また、上記心電図には「MANUAL-DLY」と記載されていました。そこで、私たちは心電図モニターのメーカーにいわゆる弁護士法23条照会を行い、その結果、「MANUAL」とは手動を意味し(自動記録は「ALM」と記載される)、「DLY」は遅延記録を意味し、手動で記録キーを押すと9秒前の波形から記録されることが判明しました。したがって、本件心電図記録は患者心静止後の手動による記録であり、記録キーを押す9秒前から記録されたものであることが明らかになり、自動記録されたものという相手方クリニックの主張は虚偽であったことが明らかになったのです。したがって、「心電図に前駆症状がないから敗血症による心停止とは言えない」との一審判決は維持できなくなったのです。
しかし、相手方クリニック側はそれでも心電図モニターは自動記録される設定になっていたと言い張るので、当方が「それでは自動記録された死亡直前の心電図を提出されたい」と要求したところ、「保管していない」(つまり廃棄した)との回答でした。これほど重要な記録を廃棄したとは驚くべきことです。当方がそれを指摘すると、クリニック側は今度は「いや、心電図モニターは最初から自動記録されない設定になっていた」と主張を変更し、その主張の変転ぶりは目を覆うばかりでした。結局「看取り治療」を決め込んだ担当医師がAさん死亡後、単に死亡確認のために手動で心電図を記録したというのが真相です。
以上のようなやりとりをふまえ、また、控訴審でも新たに提出した一審判決を批判する協力医師の意見書をふまえ、仙台高等裁判所はCさん勝利的和解案を双方に勧告し、結局クリニック側もこれに応じ(判決になればさらに高額の賠償額になることが予想されました)、平成29年2月和解が成立したものです。最初の相談から足かけ5年が経過しており、Cさんも私も感無量です。
6 私が見るところ、高齢者の治療の場合、早々に「看取り治療」を決め込み、十分な救命治療を怠る医療機関が少なくないように思えます。本和解はそのような医療現場に大きな警鐘を鳴らすものと言えます(文責・弁護士菊地)。
医療過誤訴訟、高裁で逆転勝利和解成立!